自分史やレジリエンスについて解説しています!
アニメ「AIの遺電子」の第5話「調律」の考察です。
瀬戸「お前ももっと嘘に寛容になれ。嘘をつきとおす技術はとうに揃ってるんだぜ」
光とは治療方針が根本的に異なる医師・瀬戸が登場しました!
患者が手っ取り早く幸せになるために、正規の治療法ではないやり方で記憶の改竄を行うなど、時には嘘を上手に利用していましたね。
では瀬戸が間違っているのかと問えば、そう言い切れないのが難しいところです…。
人生は有限ですし、若いうちにリセットしてやり直すことができるとしたら、縋りたい人はたくさんいそうですね。
- 自分史を繰り返す意味は?
- レジリエンスとは?
- サボテンの花は何を意味するのか?
- 個性は進化の先駆け?
前回の考察はこちら👇
このページはアニメ「AIの遺電子」の5話のネタバレを含みます。
5話をご視聴の後で読んでいただけると、より楽しめます。
自分史を繰り返す意味は?

6年前、瀬戸は松村を治療する際、自分史を繰り返してもらっていました。
自分史というのは、その名の通り過去から現在までの経験を振り返ることです。
自分史をしっかり作ることで、自分がどのような人間でどんな考え方を持っているのか、自己分析をすることが出来ます。
松村がアルコール依存症になるに至った経験に対し、架空の人物「おじさん」を登場させ、記憶を改竄していったようですね。
レジリエンスとは?

瀬戸「MICHIも大人のレジリエンスは高めてくれないぜ」
アニメ「AIの遺電子」5話「調律」
レジリエンス(resilience)というのは、困難にぶち当たった時にそれを跳ね返す力のことを指します。
以下、レジリエントな人の特徴をいくつか挙げてみました。
- 周囲と良好な人間関係が築ける
- 柔軟な考え方ができる
- 失敗してもすぐ立ち直り、その経験を糧に成長できる
- ありのままの自分を受け入れ、他人と比較しない

皆さんはどれくらい当てはまりましたか?🥳
サボテンの花は何を意味するのか?

これは多肉植物のエケベリアですね。
花が咲いています。
エケベリアではなく「サボテン」と言ったのは意味があるのではないでしょうか?
サボテンの花言葉は「枯れない愛」です。

リサ「お水をあげてるんじゃないんです、愛情を注いでるんです」
アニメ「AIの遺電子」第5話「調律」
サボテンを患者とするならば、医者は水をあげる人間ということになります。
どのタイミングでどんな治療をするかは医者次第。
愛情を注ぐというのは、患者を慈しみ、制約にとらわれない治療をおこなうということかもしれませんね。
5話の感想

リスクも時間もかかる人間と違って、手軽に治療できるヒューマノイドだからこそ起こる問題を取り扱ったテーマでした。
社会に馴染めないヒューマノイドにはバグがあるんでしょうか?
バグかどうかという部分は一旦おいといて、唐突に蟻の話をしてみましょう。
個性は進化の先駆け?
蟻は餌を見つけると、巣穴と餌場を往復し始めます。
最初はみんなバラバラのルートをいくのですが、そのうち大きな行列を作りほとんどの蟻が同じルートを辿り始めます。
みんなが行く道を選択するアリは社会に適合したヒト・ヒューマノイドと言えるでしょう。
しかしたまにルートから外れて我が道を行き始める蟻もいます。
一見適合していないように思える蟻は、ごくまれに近道を見つけ出し、やがてそれが近道だと認識されると他の蟻も追随するようになるわけです。
他とは違う子を「個性だから認めてあげましょう」ではなく、その子には「今までとは違う道を見つけ出す役割があるのではないか?」と思うんですよね。
だから我が道を行く蟻を無理矢理大きな列に戻して、めでたしめでたしとしてしまうのはちょっと違和感があります。
例え学校の友達はできなくても、ユウタにはピアニストとして大成する道だってあったんじゃないでしょうか?
凡庸な音になったユウタのピアノを聴くと、ちょっともったいないなと思ってしまいました😅
私たちが今当たり前のように歩いている道も、過去に道から外れたはみ出し者が通った道のような気がしてなりません。
次回の考察はこちら👇
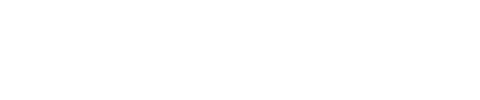



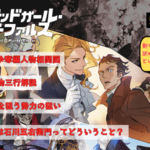

コメント
社会性は利であって、善ではない。
物語中盤男の子が暴発する直前の場面でこそ同調圧の悪、個人侵略の悪、孤立の善、暴力の悪 という対比になっていたが、
終わりは楽才の善か社会性の善かという対比になってしまっていた。
コメントありがとうございます😊
確かにピアノの才能を取るか、社会性を取るかという究極の二択になってしまいましたね。
どちらも尊いものだからこそ、ユウタのお母さんも最後まで治療を受けるか悩まれたのだと思います。
もしこの治療が人間の子どもにも適用できるなら、治療しちゃうお母さん多そうですよね😅